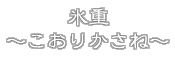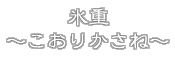ずっと変わらない日々だった。
穏やかな日々だった。
永らく時を過ごしてきた私が、どうしてそんな気を起こしたのかは今となってはわからない。
気まぐれか、戯れか。
人々から妖(あやかし)として忌み嫌われる身の私が。
妖狐の中でも特に力の強い、九つの尾を得たこの私が。
なぜ人の子供などを拾ったのか。
聞けば子供は、私を捜して深い山に踏み入ったらしい。
術を使う私に師事するために。
その子供は、微かに金色がかった朱色の目をしていた。
それだけで鬼子と忌み嫌われ、生み育ててくれた親を亡くすと同時に村を追い出されたのだと。
そして生きていく望みを、なぜか私に向けたようだった。
その望みを、私は受け入れた。
なぜ受け入れたのか。
この時の気持ちは、我が事ながら思い出せずにいる。
ただ、子供の目の色を美しいと思った事だけはよく覚えている……
あれからどれほどの時が流れたか。
歳月の意識の薄らいだ私には、皆目見当がつかない。
しかし、子供は少年へと成長した。
いっぱしの口を利くようになり、生意気な事も時折言う。
もっとも私は、この少年を養って育てているなどという概念はほとほと無に等しいのだが。
物事の分別も既につくであろうに。
それでも少年は私の元から離れようとはしなかった。
「なあ、ししょー」
「……その『師匠』という呼び方をやめろ」
「名前わかんねーんだもん。他にどう呼べっていうんだよ」
確かに、私の名を少年には教えていなかった。
私は少年の名を知っていたが、少年は私の名をしつこく問う事はなかった。
名前、というものは特別なものだ。
それだけで相手を縛れるほど、力強く、特別な言霊。
「それに、生きるために必要なことや、ちょこっとだけだけど術も教えてくれてる。
あんたは俺にとって絶対の師匠だ」
「……物好きだな、お前も」
「ししょーに言われたかねーやい」
私の揶揄するかのような言葉にも。
少年は、照れたように笑った。
人が踏み入る事をためらう場所は、自然が厳しく牙をむく。
この冬もそうだった。
吹き荒ぶ雪。
厳しい寒さ。
人ならざる身の私にはさほど堪えないが、人である少年はそうもいくまい。
軽く尾のひとつを動かし狐火をいくつか灯してやるも、結局は僅かな時のしのぎにしかならない。
自らの体躯を抱えるようにしてうずくまる様子を見遣り、私は軽く息を洩らした。
「この寒さは堪えるだろうに……」
「へ、平気だいっ。このくらいっ」
その言葉がどこからどう見ても強がりでしかないのは、明白だった。
身体は震え、歯はうまく噛み合わずにがちがちと細かく鳴っている。
やや間を置いて、私は少年の名を呼んだ。
滅多に呼ぶ事のないその名を、呼んだ。
「…………来い。こちらへ」
少年の表情が、何事が起こったかと理解していないものになった。
動きが止まり、口を僅かばかり開けて。
おそらくこの瞬間は、寒さすら忘れている事だろう。
「ししょー……?」
思考は理解せずとも身体は理解したのか、言葉と同時にそろりと足が動いた。
傍らまでその身体が来ると、尾のひとつをまとわせ寄り添わせる。
そのまま、残りの尾でくるんでやるように少年を包んだ。
「あ……あったかい……」
「これで少しは凌げよう……」
「うん……ししょーのしっぽ、すっげーあったかいよ」
どこか嬉しそうな少年の言葉は、暖かさからか微睡みをはらんでいた。
そのまま寝かしつけようかとも思ったが、もう一度少年の名を呼ぶ。
「なに、ししょー……? 今日は珍しいね……」
我ながらどうかしている、とも思う。
自らがこれから紡ごうとしている言葉を思うと尚更に。
「師匠、ではない……私の名は、琉詠(りゅうえい)だ」
触れ合いを知った。
心を知った。
――互いの名を知った。
End.
あとがき
構想30分〜1時間、執筆トータルでおよそ2時間と少し(推敲・改稿込)
キーワードは、無気力、昼行灯、少年、師匠。なんだろう、この節操のなさは……
初期に浮かんだ3つのお話の中で、一番最初に書き上がりました。
これが書き上がったおかげで、連作が生まれる結果にもなり。
『琉詠』とのお付き合いは、まだまだ続きそうです。
「刻散りて 言の葉は巡り」トップ 小説トップ サイトトップ